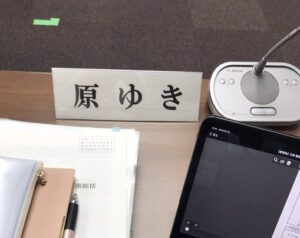令和7(2025)年第2回定例会~一般質問~
ご報告が大変遅れてしまいましたが、ここからまとめてご報告してまいります!
一般質問で行った質問をまとめました。
関心のあるトピックをクリックしてお読みいただければと思います。
※記事は概要です。質問の様子(議会インターネット中継のアーカイブ配信)は以下からご覧いただけます。
Topics
テーマ1 立川の未来の教育について
Q.(原ゆきの質問)今般、学校、家庭以外の「サードプレイス」の重要性が注目されている。こういったことには、教育委員会だけでなく、子ども家庭部をはじめとして市長部局との連携が重要視される。これまで教育長が教育現場で実態を把握されてきたことを含めて、何を大切に考えるのか、改革をすすめるべき項目は何か、その大きなビジョンについて聞く。
A.(市の答弁)まず、第4次学校教育振興基本計画素案においてお示しした通り、誰一人取り残さない、多様な人々がと共に生きる社会の実現に向けた学校教育を推進していく。また、学校や家庭、地域社会と連携、協働して、今を生きる子どもたち、全ての子どもたちの成長を支え、これからの社会を生きていくために必要となる確かな力をはぐくむということに取り組んでいく。
①子どもたちをとりまく環境について~教育と福祉の連携で、誰一人とり残さない立川の教育行政を~
Q.本市では不登校の児童・生徒が増加傾向であり、その理由も複雑化・複合化している。学校だけでは解決が難しい内容について、福祉部門との連携が今後重要になってくるかと考える。不登校傾向にある子どもたちの課題解決にむけた、市長部局との連携の在り方についての考えは。
A.学校では、一人ひとりの背景やニーズを理解し、尊重する教育的な視点で指導、支援をしているが、不登校の背景にある課題、貧困や虐待、ヤングケアラー、社会的孤立などの解決にむけた支援も必要と考える。ここ数年の取り組みの中で、スクールソーシャルワーカーの活用が進み、福祉的な視点でのサポートが浸透している状況。、あた。市長部局の重層的支援会議や地区ごとのブロック会議などにおいては、多様な支援を必要とする児童生徒の情報共有を図っている。特にヤングケアラーに関しては令和6年度実施のアンケート結果を活用し、市長部局と連携して、対象者への支援について検討していく。今後、さらに連携を強化した上で、不登校児童生徒の多様な背景にアプローチしていく。
Q.不登校支援に関する取り組みの具体例として、東京都の事業を活用しての校内別室指導があるが、期間が定められたものであり、なかなか市内全校で対応できるというものにはなっていない。仮想空間を活用したバーチャル・ラーニング・プラットフォームも導入されたが、昨年、東京都から付与されたアカウントは約60あり、1月末時点で実際にアカウントを配布した生徒は19人とのことで、全アカウントの3分の1程度しか利活用に至っていないということになる。学校に行きづらさを感じる子どもたちの居場所として開設している教育支援センター、小学校は柏小学校のおおぞら、中学校は錦学習館のたまがわで不登校支援を行っていただいているが、不登校児童生徒で報告されている全体数からみると、登録者数は約2割程度にとどまっている。本市で取り組む不登校対応について効果が見られていること、不足していること、今後さらに進めていくべきことなどについて、見解は。
A.誰一人取り残さない教育の実現にむけて、多種多様な不登校支援対策を提供したこと、また、個別のケースにはなるが、このいずれかに不登校児童生徒がつながることができたことは一定程度評価できると捉えているが、全て網羅的にということではなく、それぞれ課題は抱えているところ。今後については、魅力的な学校づくりを支援し、児童生徒の学校生活の充実度、満足度を高め、不登校の出現を未然防止することが大切であると捉えている。また、それぞれの取り組みをより効果的に活用するということについては個別に振り返りをしていく。
Q.子育て世代では、両親フルタイムで働く共働きや、多様な働きを選択する場合が増えている。また、家族のかたちの多様化等により変容する社会の状況から、学校、家庭以外の「サードプレイス」を教育部と市長部局がタッグを組んで、場合によっては社会福祉法人やNPO法人、民間企業、地域の方々とも連携して、子どもたちが安心して過ごせる多様な居場所を創出していくことが必要であると考える。例えば足立区では、国の交付金を活用して、学校で朝ごはんの取り組みを行っている。各小中学校に予算をつけて、朝食が食べられない厳しい家庭環境にある子どもにおにぎりやパンなど簡単なものを提供するというもので、中には地元企業が寄付する食材を使って、家庭科室を活用し、教職員ではなく地域の有志の皆さんが朝食を提供する小学校もあるという。地域や、本市の福祉部門と教育部が連携して子どもたちの居場所を創出していくことについての見解は。
A.子どもたちの多様な居場所づくりについては、引き続き教育委員会と市長部局が連携して取り組んでいく。一方で、学校をこどもたちの多様な居場所づくりの場所とした場合には、子どもたちの安全性などを確保する上で、様々な課題やリスクなどについても考慮する必要があると考えている、学校現場とも相談しながら研究、検討を進めていきたいと考えている。
Q.すでにもっている地域の資源として、児童館や学童、図書館、子ども食堂、地域福祉アンテナショップ等、子どもたちも利用できる地域の居場所をたくさん用意していただいている。そういった居場所につなげるためや子どもたちに寄り添うためにスクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーなどの専門職が学校現場にも入っていただいていいるが、役割について聞く。
A.スクールソーシャルワーカーは、いじめ、不登校、暴力行為、児童虐待等、生活指導上の課題に対応するため、小中学校からの要請に応じて支援を行う。教育分野に関する知識に加え、社会福祉等の専門的な知識や技術を用いて、児童生徒が置かれた様々な環境に働きかけたり、関係機関等とのネットワークを活用したりして、課題を抱える児童生徒及び保護者に対して支援をおこなっている。一方、スクールカウンセラーは、不登校やいじめ、児童虐待等の未然防止、早期発見等、児童生徒の悩みや抱えている問題の解決に向けて、児童生徒や保護者からの相談に応じ、面談を行ったり、授業観察等を通して、支援に必要な情報を収集し、教員へ助言や援助をおこなっている。
Q.スクールソーシャルワーカーの活用は現状、校長先生の判断によるもの、つまり学校の要請に応じて派遣するというスキームになっている。またスクールカウンセラーは東京都の非正規雇用の職員であり、各校の相談室への来室は週に1回とのこと。こういった現状による課題等把握しているか。スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーがもっている力をさらに発揮し機能できるような体制づくりなど、今後の展開として考えていることは。
A.まず、スクールソーシャルワーカーは、今年度より主任スクールソーシャルワーカーを1名から2名に増員し、他のスクールソーシャルワーカーに対して助言を行う体制を整えた。これにより、他のスクールソーシャルワーカーが1人でケースを抱え込み、適切な支援が難しくなる状態に陥ることを防止し、円滑な課題解決につながることが期待できる。また、スクールカウンセラーに関しては、教育相談活動の充実を図ることを目的に、スクールカウンセラー連絡会を年2回設定し情報交換を行っているところ。
②教職員の働く環境改善について~先生と子どもたちが過ごす時間の充実にむけて~
教員給与特別措置法、いわゆる給特法の改正案が国会で審議の渦中となっている。先日衆議院では修正が加えられ、時間外勤務の削減目標などが付則に盛り込まれて可決された。現在は参議院で審議中であり、今国会で成立する見込みとなっている。この改正案では、教員の処遇改善と働き方改革を目指すもので、残業代の代わりに支払われる教職調整額4%を6年後までに段階的に10%に引き上げることが主な内容となっている。本市の小中学校教員の時間外在校等時間、これまでの資料からも月に45時間以上の超過勤務をしている教員は、令和2年に小中学校全体で65.7%のところ、令和5年度64.1%。80時間以上のような、継続すれば過労死ラインといわれるような働きの部分の数値は若干減ってはきているものの、全体ではまだ半数以上の多くの教員が月40時間以上の超過勤務をしている。いくら残って働いてもそこに残業代の手当てはなく、一律4%の教育調整額に支払いで済まされてしまっているのが現状。それでも何とか先生方が、子どもたちと向き合う時間をもつことができるよう、あるいは教員の教材研究や授業準備の時間を確保するため、柔軟な教育課程編成の促進が推奨されている。例えば、八王子市では、市として総授業時数は標準授業時数に18単位時間を加えた時数を上限とし、週当たりの授業時数は28単位時間を上限とする指針を示し、所管の学校に指導・助言を行っている。各学校がこれを踏まえて教育課程編成を工夫し、全ての小中学校で週当たり授業時数を27単位時間または28単位時間とする教育課程編成を実現したという。また、渋谷区では、総授業時数の計画が標準授業時数となるよう、つまり計画時点で小学4年生以上なら1015時間を超えないということを区域の学校に指導助言している。また、目黒区では文科省の「研究開発学校」の指定を受け、「40分授業午前5時間制」の特色ある教育課程の開発に取り組んできたということです。現行、小学校では1単位時間45分のところ5分減らして40分で一つの授業を組み立てるということだ。このような導入例は全国的に広がっており、学校の授業時間数や教科増加に伴う負担感を減らすこと、子どもの学び方の改善を目指した取り組みとして注目されている。昨年12月の一般質問で私が、緊急提言と示された上限1086時間について本市の状況を聞いた時、令和4年度の市内小中学校の年間授業時数の実績は、小学校5年生の平均で1041時間、中学2年生で1063時間ということだった。平均ということなので、この数字よりさらに多い学校もあるかと思えばやはり改めて考えると多すぎる、カリキュラムオーバーロードの状況になってしまっていないかという懸念がある。そこで、教員や子どもたちのために、こういった柔軟な教育課程の編成についての見解聞く。
A.令和6年12月25日に中央教育審議会に諮問された初等中等教育における教育課程の基準等の在り方についての主な内容については、質の高い、深い学びを実現し、分かりやすく使いやすい学習指導要領の在り方、多様な子どもたちを包摂する柔軟な教育課程の在り方、各教科等やその目標、内容の在り方、教育課程の実施に伴う負担への指摘に真摯に向かうことを含む学習指導要領の趣旨の着実な実現のための方策となっている。今後の動向に注視し、立川の子どもたちが充実した学校生活を送れるよう検討し、教師の余白を生むということについては研究を進めていく。
Q.今回の給特法改正案では、時間外勤務を平均30時間まで削減することや、教員の業務量を適切に管理する計画の策定・公表を教育委員会に義務づけ、その計画の実施を学校に義務づけることなどが盛り込まれている。持ち帰り時間や部活動など学校外での時間も含めた把握についての見解を聞く。
A.文部科学省が令和4年度に実施した教員勤務実態調査の集計結果によると、平日の持ち帰り時間は全国平均で小学校が37分、中学校で32分、土日の持ち帰り時間は全国平均で小学校が36分、中学校が49分となっている。また5年度に実施した部活動の実施状況等調査で、週休日に毎週活動している部活動の割合は、運動部が78.6%で文化部では14%となっている。なお、立川市独自で勤務実態調査を実施する予定はないが、学校行事の精査や業務の見直しについては各学校に指導していく。
Q.今回の改正法案におきまして、教育委員会に対して、教員の業務量の管理、また健康確保の措置実施計画の策定が義務づけられることとなっている。教職員の健康確保措置について、人事委員会を置かない自治体においては首長においてどのように機能させると考えるのかが注目される。現状では教員の勤務時間を各校長に、メンタルヘルスを都教委に任せ、管理職にするのが難しい相談窓口がはっきりしていないような現状から一歩進めなければならないと考えるが、見解は。
A.現状については、教員のための相談窓口としてSNS、いわゆるLINEによる相談窓口、電話での精神保健相談、メールによる相談等を東京都が用意しており、市教育委員会では教員への周知を図っているところ。
Q.労働安全衛生法・労働安全衛生則に基づく産業医の配置については、50人未満の事業所(学校)複数校合わせての配置等が推奨されている。労安についてはこれまでも市職の労働安全衛生委員会に教職員も含めていただけないかと訴えてきたが、検討状況は。
A.平成31年4月に文部科学省が作成した「学校における労働安全衛生管理体制の整備のために」、第3版において、教職員49人以下の学校においても、産業医の要件を備えた医師等を採用し、複数の公立学校の教員の健康管理を担当させる等の取り組みもゆうこうであると示されており、このこと自体は承知している。教職員の心身の健康があってこそ、子どもたちの学校生活の安定が図られると考えており、今後、各地区の設置状況を調査した上で、本市としてはどのような方策がとれるのか検討していきたいと考えている。
テーマ2 もっと!出産子育てしやすいまち立川へPart7
Q.この度、子育て支援・保健センター「はぐくるりん」が今月7日、職員の皆様のご尽力をもって、無事オープンとなった。当施設では、子ども家庭センター、児童発達支援センター、教育支援課といった子育て関連部署を集約するとともに、部署間が有機的に連携することで、子どもの成長過程に応じた切れ目ない適切な支援が提供される。子育て支援の拠点として、関係する多くの部署がはぐくるりんに集約されたことによる、母子保健部門と児童福祉部門との連携体制の変化について聞く。
A.子ども家庭センター、児童発達支援センター、教育支援課といった子ども・子育ての部署が集約されたことで、子ども・子育て家庭に対して、妊娠期から18歳まで切れ目なく包括的な支援を提供しやすい環境が整ったと考えている。開所から1か月が経過し、同じ地区を担当する保健師と相談員などが、課や係を超えて、事務室内に設けられたファミレス風ブースで打合せする姿などがよく見られます。こうしたことで、迅速な情報共有やスキルの継承が進みやすくなり、各専門分野が連携した適切な支援につながっていくものと考える。
①各地域に焦点化した子育て支援を
Q.子ども家庭センターを包含し子育て支援を統括する新たな施設ができたわけだが、場所が立川駅の南側、錦町3丁目ということで、立川駅では中央線線路を挟んで南側、また立川駅から歩いても多少距離があり、住んでいる地域によってはアクセスしにくい、特に北側エリアにお住まいの方々から、そういった声があるのも実際のところ。子育て支援ということでは、住んでいる地域によって差がでないよう、誰もが等しくサービスを受けられることが理想であると考える。就学前のお子さんとその保護者、妊婦を対象とした親と子の健康相談があり、心理相談も行っていただいている。これらの相談ははぐくるりんが基本だが、2か月に1回のペースで西砂学習館・上砂会館にも出張して取り組んでいる。また、パパママ学級や各種検診などはぐくるりんでしか受けることのできないサービスがある。これらは砂川エリアも含んだ市の北部地域に住む親子にとっては、はぐくるりんの場所に訪れるだけでも相当なハードルとなる場合があり、そういったサービスをもっと身近な地域でも受けられるようになれば、さらに多くの市民の不安や悩み解消につなげていけるのではと考えている。こういった事業・サービスを各地域へアウトリーチしていく、出張相談の拡充などについての見解を聞く。
A.はぐくるりんの立地については、これまでも施設建設の説明会等の場で、交通の不便さや、乳幼児を連れて移動することの負担感のご意見とともに、アウトリーチによる開催のご要望をいただいている。現在のところは、開所したばかりであり、今後の来館状況等を注視し、利用者の声をお聞きするとともに、現在建設中の砂川学習館内のひまわり子育てひろばの活用も視野にいれながら検討していきたいと考えている。
Q.子育て支援サービスのアウトリーチの会場の一つとして、例えば現在跡地活用が検討されている、旧若葉小学校、これから事業者の方募集していく段階かと思うが、入っていただく事業者にご理解いただけるなら1室でも市で確保して、そういった利活用をすることはできないのか。
A.旧若葉小学校については、若葉町まちづくり方針に基づき、様々な利活用を検討中と聞いている。はぐくるりんの利用状況を注視し、利用者からのご意見を聞きながら、アウトリーチの必要性、実施する場合の施設や事業内容などについて検討していく。
Q.はぐくるりんは子育て支援のハブとしてあって、地域の課題は各地域で解消していけることが最適なのではないかと思っている。そこで、地域の公共施設、例えば公立保育園などで、母子が気軽に立ち寄れて、相談や支援ができるなど、より地域に焦点化していくことで、母子支援がダイレクトに届いていくのではと考えるが。
A.ご提案の趣旨の具現化がまさに市内各所で開設をしている子育てひろばであると考えている。身近な場所で乳幼児連れの保護者が気月に集い、相談や交流ができ、誕生日会などのイベントや保健師や栄養士による講座等も実施をしている。公立保育園においても、地域の子育て相談を受け付けるとともに、園庭開放や出張イベントなども行っているので、ぜひお気軽にお立ち寄りいただけるよう、内容の充実と周知に努めていく。
②子どもの声をきくことについて
Q.本年4月25日号の広報たちかわで、広聴制度のお知らせについて掲載されていた。皆さんの「声」をお聞かせくださいということで、寄せられた声が紹介されていた。その「声」は小学生からのもので、内容としては小学校の近くに児童館がなく、暑い日や雨の日でも友達と遊べる場所がほしい、ということだった。児童館、市内に9館あるが、小学校の近くにない場合がある。市内にはこういった地域がいくつもあるのか。
A.児童会館含め9館の児童館は、全ての小学校周辺に配置されているわけではないため、立地上、学区域を越えなければならない児童館もある。
Q.小学生から寄せられたご意見には続きがあり、「出張児童館もあって楽しみにしていたけれど、小さい子ばかりで一緒に遊べる子がいませんでした。児童館のおたよりにのっているイベントを、小学校の近くでもたくさんしてほしいです。」ということだった。今回私自身この出張児童館の取り組みを始めて知ったこともあり、経緯や目的についてお示しいただきたい。
A.出張児童館は、児童館で行っている遊びや工作などを児童館以外の場所でも子どもたちに楽しんでもらおうと実施している取り組み。また、その活動を地域の皆さんに知っていただくことが、地域での理解や関係づくりにつながるとも考えている。児童館では日頃から、運営協議会などの機会を通じて、放課後子ども教室運営委員会や子ども会連合会など、地域の子どもたちのために活動している諸団体の皆さんと情報交換や交流を行っているので、ご意見やアイディアをいただくことも多く、プログラムの企画に生かしている。
Q.出張児童館の取り組みが貴重なものである地域によっては特に、その子たちが、そういった機会を逃すことのないよう周知をしていただきたいと考えるが、見解は。
A.今回の出張児童館開催の告知は、小学校を通じて配布をしている児童館だよりに掲載をしていたが、当該会場での実施が開始して間もない取り組みであったため、来場者が少なかったと聞いている。今後の出張イベントの周知については、安心して参加いただけるよう、場所のご案内を含め、分かりやすい配慮や工夫をしていく。
Q.今回声を寄せてくれたお子さんは、意見を伝えれば耳を傾けてくれる、実現にむけて市長をはじめ市職員の皆さんが一緒になって考えてくれるということを実感できたとても喜んでいたと保護者の方から聞いた。子どもの意見表明権を尊重するという点においても大変すばらしいやりとりだったと感じた次第。子どもたちが自分の意見や思っていることを伝えていいんだということ、立川市として全庁的に子どもの声を受けてそれに応えていっていただきたいと考えるが、見解は。
A.子ども当事者の意見表明及び施策への反映に当たっての必要な措置は、こども基本法第11条において国や地方自治体に義務づけられている。このことを踏まえ、策定した第5次長期総合計画前期基本計画の基本事業の中に、様々な場面で子どもの主体的な活動を応援していく地域づくりを進めることを明記した。子どもや若者は、社会を共につくるパートナーであるとの視点に立ち、取り組み自体の周知にも努めていく。
③保育園や一時預かり保育に子どもを預ける保護者負担の軽減を
Q.一昨年、令和5年12月議会で保育施設での紙おむつ定額制サービス導入について求めている。当時、その前年度から公立保育園での導入について検討を行っており、保護者アンケートのほか、懇談会での意見交換や導入済みの施設へのききとりなどにより導入の是非について検討していきたいという旨のご答弁であった。その後の進捗状況は。
A.公立保育園への紙おむつの定額制サービスの導入については、保護者懇談会の中で直接ご意見をお聞きしたり、導入済みの施設への視察を行ったりするなど、その後も検討を続けてきた。サブスク利用児とそうでない児童が混在することによるオペレーションの工夫や、本市公立園の収納スペースについては、引き続きの検討課題であり、現時点では導入決定に至っていない。
Q.また、いまやおむつだけでなく、寝具類、お昼寝コットカバーのサブスク、保育園向け寝具レンタルサービスなんていうのも出てきている。寝具類のアウトソーシングについて、見解は。
A.本市の公立保育園では、布団は保育園で用意することにし、保護者の皆さんのご負担をなるべく軽減するよう努めている。ただし、シーツについては、保護者の荷物の状況やご兄弟での在園等により、お持ち帰りの際に大変そうなご様子をお見かけすることもよくある。
Q.市内で土日の一時預かりを行っているのは未来センターの「みらいっこ保育室」のみなのだが、予約は電話で、日曜日にいたっては往復はがきでの予約申請となっている。この点、利用者の利便性も鑑みればウェブ申請ができるよう早急に取り組んでいただきたいと考えるが、見解は。
A.子ども未来センターの一時預かりは大変人気が高く、過去に先着申し込みの競争が過度となり、問題となったことから、現在のはがきが採用された経過があると聞いている。しかしながら、現在はスマートフォンなどのツールが一般化し、予約方法についても見直していく必要があることは、市としても認識しており、現在、一時預かりを運営する指定管理者と共に、ウェブ予約システムなどの導入可能性について検討しているところ。引き続き、保護者のご意見も聞きながら、皆さまが利用しやすい保育サービスの提供に努めていく。