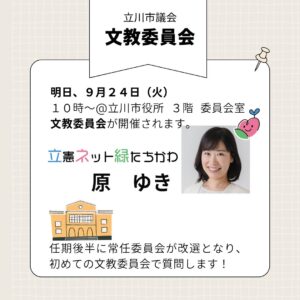2024年第4回定例会ご報告~一般質問~
一般質問のまとめを投稿します。
関心のあるトピックをクリックしていただければと思います。
忙しない年末、交通事故が増えたり体調を崩されたりする方も多い時期になります。
どうか皆さまお身体お大事にお過ごしくださいますように。
※記事は概要です。質問の様子は以下をご覧ください。
Topics
性の多様性が尊重される地域社会の実現を
これまでの経緯
多様な性、LGBTQ、SOGIなど、現代社会では性的マイノリティの方々に対する理解が深まってきている。今では人口のおよそ8%、性的マイノリティの方が存在するとされ、利き手が左利きの方、血液型AB型の方と同じくらいとも言われている。立川市においては、過去に「同姓パートナーシップの公的承認についての陳情」、及び「パートナーシップ制度・ファミリーシップ制度に関する陳情」がいずれも全会一致で採択された。東京都のパートナーシップ宣誓制度は、婚姻届けによらずパートナーであることを証明する制度として2022年11月1日から制度の運用が始まり、開始以降、多摩地域においても、独自の取り組みとして性の多様性を尊重する条例やパートナーシップ制度を制定している自治体は少なくない。しかしながら、立川市においては未だ制度の制定には至っていない。私は今回、「同姓パートナーシップの公的承認についての陳情」を提出された陳情者の方にお会いして、お話を伺った。「せっかく自分が種をまいたのに、花が咲かないまま枯れてしまったのか、3年も何の動きもない。レインボープライドに参加しても、多くの近隣自治体のブースがあるのに、立川市のブースがなくて本当に残念に思う。もう諦めていた」とおっしゃっていた。性の多様性を尊重する本市の取り組みについて、改めて、これまでの経緯をお示しいただきたい。
A.多様な性への対応としては、立川市第7次男女平等参画推進計画に明記し、性的指向、性自認について尊重し、周知啓発に努めてきているところ。令和4年11月からは、東京都パートナーシップ宣誓制度が始まり、本市では、この東京都の制度に基づき、軽自動車税の申請や市営住宅の申し込みが利用できるよう対応してきている。また、令和5年度には、男女平等参画についての市民アンケートを実施し、性の在り方について調査を行うなど、性の多様性への対応に取り組んできている。
Q.第7次男女平等参画推進計画には、基本テーマ1「男女平等参画と人権の意識づくり」のなか、「多様な性への尊重の促進」の事業において「職場を含む市民生活の全てにおいて、偏見や差別、ハラスメント等が起きないよう、あらゆる性的思考・性自認を尊重するための啓発を行う」という内容があります。具体的にどのようなことを行ってきたのか。
A.人権の意識づくりとして、女性総合センターアイム登録団体による企画講座や、性的マイノリティー当事者による職員研修、市立中学校3年生を対象とした人権教育、性教育の出前講座などを行ってきている。また、職員が性の多様性について正しく理解し対応できるように、性の多様性を理解するハンドブックを作成し、現場のほうで活用している。
Q.私は今回日野市の平和と人権課へ伺いお話を伺ってきた。2022年令和4年12月、日野市では男女平等基本条例が改正され、翌2023年令和5年4月1日より施行、同時にパートナーシップ制度が始まった。本条例の改正にむけて、すべての人の性別等が尊重され多様な生き方を認め合うため全庁的な調査を行い、関連する改正があったという。2021年、令和3年度にまず男女平等課を中心に組織改正を行い、平和と人権課が設置されたのがその大きな考え方を表している。平和や人権を大切にし、多様性、いわゆるダイバーシティを認め合う社会を作るため、男女平等や多文化共生を推進していくというもの。立川市第7次男女平等参画推進計画の中には、あらゆるところに「男女」という文言が目立つ。個人としてその人らしい生き方を尊重するのであれば、性的マイノリティの方の存在や生き方にも思いを馳せて、「あらゆる性」や「性別にかかわらず」、あるいは「ジェンダー平等」などの文言に改めるべきところは改めて、時期計画に向けてもう一度見直してはと考えるが、見解は。
A.従来の男女平等だけでなく、性別にかかわらず全ての人が平等な社会の実現が求められている。男性と女性の賃金格差や性別役割分担意識の解消など、男女平等への取り組みは引き続き必要であり、LGBTQに関する施策も重要であると認識している。この「男女」という文言については、次期計画策定の審議会等に諮りながら、丁寧に進めてまいりたい。
Q.本市においては2021年令和3年第4回定例会にて「同姓パートナーシップの公的承認についての陳情」が、また、翌2022年令和4年第2回定例会では「パートナーシップ制度・ファミリーシップ制度に関する陳情」がいずれも全会一致で採択されました。それ以降の庁内での協議やそれらに向けての検討状況をお示しいただきたい。
A.陳情が採択されたことを受け、多様な性に関する制度を検討するため、庁内の関係部署で構成した「立川市多様な性の制度検討委員会」を庁内で立ち上げている。これまで東京都パートナーシップ宣誓制度導入を受け、本市での制度の活用についての検討などを進めてきた。また、次年度以降にむけ、パートナーシップ宣誓制度の本市での活用についても、この中で検討しているところ。
Q.本年第2回定例会で示された第5次基本構想素案概略を見ると、第3章「立川市の現状と展望」の中の「社会潮流の変化」という項目があり、さらに「多様性を尊重する社会の実現」として、「多様な性の在り方」とある。内容をみると、「性的マイノリティの方の認知と理解が進み、性的思考や性自認の多様性を尊重する風土が形成されつつありますが、権利の向上や差別解消に向けた更なる啓発活動が求められます。」と書いてあって、まさにその通りだと共感するところだが、ここで言うところの「差別解消に向けた更なる啓発活動」とは、具体的にどのような取り組みを想定するものか。
A.第5次基本構想の素案では、人権への理解が広がり多様性の尊重が進む一方、ネット上ではいじめや人権侵害が生じていますとの現状の課題を記載しているところだが、同時に偏見や差別を受けず誰もが自分らしく生きられる社会の実現には、あらゆる年代を対象とした啓発活動が今後も重要であると考えている。具体的な取り組みに関しては今後の検討となるが、幼少期からの学びは重要な要素の一つであると考えている。
Q.同様に第3回定例会では、第5次長期総合計画政策・施策体系の中に総合戦略として「男女平等参画社会・多様性の推進」という施策において「性の多様性に関する言葉の認知(アンケート)」とある。そのアンケートの内容やその後の活用の予定などについて聞く。
A.令和5年度に男女平等参画についての市民アンケートを実施し、性の在り方についての調査を行った。性の多様性に関する言葉については、性自認、性的指向、LGBTなど認知が浸透しているものがある一方で、SOGIなど普及していない言葉も見られた。性の多様性についての理解を客観的に把握できる指標として位置付け、誰もが自分らしく生きられる社会の実現を目指してまいりたい。
Q.庁内設置された立川市多様な性の制度検討委員会において、パートナーシップ宣誓制度の本市での活用について検討しているということで、本当に嬉しく思います。求められた方々にとっては、具体的に生活が変わってきたり、心の支えになったり、いろんなメリットが今後でてくるのだと考え、今後の取り組みにも引き続き注目したい。現在の検討状況について、聞く。
A.このパートナーシップ宣誓制度に向けては、現在導入に向けた検討の準備を進めているところ。今後の進め方として、この性的マイノリティー当事者の人権尊重の一つとして、当事者の声をしっかり伺いながら、準備も併せて進めていきたいと考えている。
Q.日野市でお話伺った際、日野市でパートナーシップを宣誓された方の証明書を見せていただいた。自治体独自の制度と東京都の制度どちらも宣誓をする、あるいは、東京都だけ、住んでいる自治体だけ宣誓するといったように、その方の考え方によっても様々だが、東京都の宣誓制度は電子なので、証明するものが手元にないという。日野市のように、宣誓書や民間サービスを利用するときにも証明になるような持ち運べるカード形式のもの、こういった手元に持てるものがあると、実感として感じやすく、当事者の方から大変好評であるとのこと。また、制度の開始にあたって市の広報でお知らせをして、実際に宣誓された方のお声などを掲載して制度の周知を行ったそうである。今回、条例制定された町田市でもお話を伺ってきたのだが、町田市も日野市も、パートナーシップ制度を利用する当事者向けに利用の手引きを作成している。当事者の利便性向上、あるいは多くの市民に理解を得る、知ってもらうという意味ではこれらの事例も一つ効果としてあると考えるが、見解は。
A.パートナーシップ宣誓制度の導入に当たっては、当事者のみならず市民への周知啓発が重要であると認識している。先進市の事例を研究し、本市でも導入に向けて進めてまいりたいと考えている。
性的マイノリティーの方や夫婦別姓を希望する方、どんな選択も後押しできるまち立川を目指して
Q.これまでも立川市においては東京都の制度に準拠して、性的マイノリティーを対象とするパートナーシップ関係の相手方を配偶者と同等の扱いにするため、所要の改正を行ってきていることを承知している。東京都は、パートナーシップ制度を独自導入する市もしない市も、都と協定書を交わすことで都の証明書を活用可能としながら、基本的な考え方としては、「パートナーシップ制度は、各自治体が主体的に制度導入を検討しその自治体のサービスを性的マイノリティへ広げていく制度である」という姿勢を示している。つまり、多くの他自治体に例があるように、東京都の制度と地方自治体の制度は併存するものであるというのが都の基本的な考え方。今回当事者の方にお話を伺う中で、やはり自分の住むまちに制度や条例があって、初めて、自分たちの存在や生き方を認めてもらっていると思えるんだと聞いた。そして、その制度を作ることだけが目的ではなく、性的マイノリティという人権課題を啓発し、「自分らしく生きる」「ありのままに尊重される」という人権尊重の理念を、市、市民、事業者とともに考えていくことが最も大事な目的であると考える。そうであるならば、パートナーシップ制度は、異性カップルで別姓パートナーを希望するいわゆる夫婦別姓、事実婚についても認めたり、あるいはいくつかの自治体にも例があるように、子どもも一緒に家族と認めるファミリーシップ制度へとステップアップしたりしていくことで、「自分らしく生きる」その選択肢が増え、多様な選択を後押しできるまちを目指すことができる。都内で最初に異性カップルを認めたお隣の国立市では、制度開始から約2年、利用した23組の約半数が異性カップルであったと昨年6月東京新聞が報じている。また、ファミリーシップ制度については、都内では足立区、世田谷区に続き、豊島区がつい先日、11月1日から制度導入の発表があった。家族の形が多様化する現代、誰もが平等にサービスを受けられる仕組みが求められており、ファミリーシップ制度の導入によって、パートナーの子どもが外国人学校に通う際の負担軽減や、高齢の親が受ける助成金など、実際の生活に即したサポートが提供されることが期待され、利便性の向上だけでなく、災害時や病気になったときなどのためにお守りのような安心感につながるとして、当事者から求める声があります。
市民の思いを受け止めるという視点も含め、原点に立ち返り、市独自で制度の導入やパートナーとして認めていく取り組みを進めていただきたい。こういった、多様な生き方を応援する制度導入についての見解は。
A.市民一人一人が、その個性と能力を発揮し輝ける社会を築いていくことは、大変重要なことであると考えている。多様な家族の在り方を尊重し、性の多様性に関する理解を深め、誰もが自分らしく暮らしやすい社会の実現に向け、パートナーシップ、またファミリーシップへの取り組みを進めてまいりたい。
誰もがこのまちで自分らしく暮らし続けるために~医療的ケアが必要な子ども若者への支援~
「医療的ケア」とは、一般的に学校や在宅等で日常的に行われている、たんの吸引、経管栄養、気管切開部の衛生管理等の医療行為を指す。医療的ケア児とは、医学の進歩を背景として、NICU(新生児特定集中治療室)等に長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、こうした医療的ケアが日常的に必要な児童のことをいう。全国の在宅医療的ケア児は増加傾向にあり、推計約2万人とのこと。2021年9月、「医療的ケア児」を法律上できちんと定義し、国や地方自治体が医療的ケア児の支援を行う責務を負うことを日本で初めて明文化した「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」が施行された。医療的ケア児を育てる家族の負担を軽減し、医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、その家族の離職を防止することも立法の目的の一つとしてあげられている。同法には、都道府県が医療的ケア児支援センターを設置し医療的ケア児及びその家族の相談に応じること、情報の提供やその他の支援を行うことなど支援措置について示された。それに基づき、東京都は2022年9月1日、23区在住の方向けに東京都立大塚病院内に、多摩地域在住の方向けに府中市の東京都立小児総合医療センター内に東京都医療的ケア児支援センターを開設した。各地方自治体は、医療的ケア児支援センターとの連携や情報交換から医療的ケア児とその家族の生活支援・親子支援・発達支援等のサポートをすることができるとされ、その取り組みが注目される。立川市として、医療的ケアを必要とする方々へどのような取り組みが行われてきたのか。
A.平成29年度に庁内に立川市小児等在宅医療推進事業関連部署部課長連絡会議を設置し、平成31年度に外部の有識者や関係機関等を交えた立川市医療的ケア児支援関係者会議を設置した。令和元年度から2年度にかけて、同会議において実態調査やニーズ調査、事業所調査等を実施し、地域の課題や対応策を検討した結果、医療的ケア児を介護する家族の負担軽減やレスパイトへの支援の必要性から、令和4年度に重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業を開始した。また、支援事業所への働きかけとして、令和3年度に市内で放課後等デイサービス事業所と居宅訪問型児童発達支援事業所を確保し、令和5年度に放課後等デイサービス医療体制促進事業補助金を創設した。さらに、教育と保育における医療的ケア実施の在り方に関する検討を行い、令和4年度に立川市立学校における医療的ケアの実施に関するガイドラインと、立川市保育園における医療的ケアの実施に関するガイドラインの策定を行った。医療的ケア児等コーディネーターの配置については、令和5年度に方向性を検討している。
医療的ケアに関する計画について
Q.市内の医療的ケア児の人数を把握しているか。
A.現在、市内には約50名の医療的ケア児がいることを把握している。
Q.医療的ケア児支援関係者会議を何度か傍聴させていただいた。実際にケアや支援を行う医師、医療的ケア児支援センター職員、生活を支える児童発達支援事業所や相談支援事業所の方、受け入れが広がってきた保育園や小学校などの関係者が委員として参加され、具体的な現場の声を広く聞くことができ、参加する委員の方から、立川市における同会議体設置について好評いただく声が届いている。こちらの支援関係者会議での意見交換や実態把握をする中で、出てきた課題は何か。
A.現在、医療的ケア児支援関係者会議で検討されている課題としては、医療的ケア児等コーディネーターの役割や業務内容のほか、市内等で活動しているコーディネーターのネットワークの構築などがある。
Q.東京都の方でも支援センターが開設をされて、今後、地域の医療的ケア児の相談や支援を専門的知見をもとにスムーズかつ適切に行うためにも、こちらとの連携が欠かせない。立川市においても医療的ケア児等コーディネーターが果たす役割が肝要になってくると考えるが、現在立川市にはコーディネーターは配置されていない。この医療的ケアのコーディネーター、多摩地域では、いくつの自治体で設置されているのか。
A.医療的ケア児コーディネーターの各種の配置状況については、現在、多摩26市中15市が配置済みと聞いている。
Q.本年3月に策定された立川市第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画を見ると、医療的ケア児に関するコーディネーターの配置人数を令和7年・2025年度つまり来年度から2名配置とあるが、市内のどこに配置され、どのような役割を果たすのか。
A.配置場所については、本庁舎を想定している。役割については、医療的ケア児等の個別支援や相談支援専門員等の後方支援などを想定している。
Q.医療的ケア児も、成長していくわけだが、先ほどの障害福祉計画・障害児福祉計画全て読んで確認したが、医ケア児が大人になる、その過程の支援の在り方や具体的な応援体制について見えづらい。他の子育て支援や福祉施策でも、18歳の壁は何かと注目されるところ。本計画についても、その支援のすき間がうまれないよう、応援体制について位置付けるべきと考えるが、見解は。
A.医療的ケア児の居場所づくりに関わる計画への位置づけについては、現在策定中の第7次障害者計画の中で協議を重ねた上で判断してまいりたい。
地域における相談支援について
Q.昨年1月30日、立川市医療的ケア児支援関係者会議を傍聴した。この時、東京都医療的ケア児支援センター・センター長の冨田先生が講師として、多摩地域の医療的ケア児支援センターの紹介や地域連携・地域支援についてお話しされていた。その際、基幹相談支援センターについて、またその果たす役割の重要性について聞いた。障害者総合支援法の改正により、令和6年2024年4月から市町村において基幹相談支援センターの設置が努力義務化されましたが、立川市では未設置である。地域における相談支援の中核的な役割を担い、多様化する相談・ニーズに対応する「基幹相談支援センター」設置に向けての状況は。
A.昨年度策定した立川市第7期障害福祉計画では、令和7年度に基幹相談支援センターを設置することが盛り込まれており、現在具体化に向けて検討を進めている。
Q.また、次年度は子育て健康複合施設・はぐくるりんが供用開始予定の年でもある。先ほど医ケアコーディネーターは本庁舎に配置とのことであったが、「はぐくるりん」が供用開始されれば、そちらの方が訪れやすい市民も多いのではと思う。はぐくるりんの拠点が、途切れ隙間のない子育て・子育ち支援の拠点となるのであれば、医療的ケアの必要な子どもたちを含む、障がいのある子の相談や手続きが、そちらでもできるようにする必要性があるかと考えるが、見解は。
A.立川市医療的ケア児支援関係者会議では、これまで医療的ケア児等コーディネーターに関することや、障害福祉課と児童発達支援センターとの連携による相談窓口や手続きに関することなど、様々なご意見をいただいている。はぐくるりんで相談や手続きができるようにするためには、人員体制や組織の問題、安定的に稼働するための財源の問題などがあり、現時点では困難であると考えている。
今後にむけて
Q.今回医療的ケアについて質問したのは、市内在住のある方の事例から、あらゆる場面での取り組みへの課題が浮き彫りになったからである。その子は、難病を抱え、日中の屋外での活動制限により紫外線防止フィルム対策等で保育園から中学校まで過ごした。児童館で元気に遊ぶ姿もあったという。立川市としてもできる範囲での対応を実施いただいたという。成長とともに車いすとなり、都立の特別支援学校へ入学、3年生になり胃ろうの手術を受け、痰の吸引と胃ろうの医療的ケアが必要となった。胃ろう手術後、学校復帰には、ケアの初期サポートとして家族が10日ほど学校に付き添い、状態が安定したら学校配置の看護師にバトンを渡していく制度になっている。生活のために仕事をしなければならない母親は、過去の手術入院時に休職していたが、退院後も学校へ通学するために、さらに10日間ほど学校への付き添いを余儀なくされ、生活面仕事継続面等大きく頭を悩ます問題となり、学校からも社会からも見放された気持ちになったと話していた。利用している放課後等デイサービス事業所の応援で何とか10日間乗り切った。
しかしまだ壁が立ちはだかっていた。医療的ケアが必要となったことにより看護師存在の通学バスが学校で対応できず、朝は自宅から40分はかかる特別支援学校まで送り、学校受け入れ規定時間の8時45分を待ち、急いで引き渡し、そこからまた30分以上かかる職場へ駆けつける毎日。9時からの仕事には間に合わないため、始業時間を遅らせてもらっているとのこと。学校の送迎があれば、せめて学校での引き渡し時間を融通してくれれば、と願うも、厳しい公的支援の現状から叶わず、医ケア児とそのご家族が抱える課題が随所にあることが分かった。
成長に合わせて、18歳の若者の卒業後の居場所は、新たな社会に参画する、そのための学びや体験等、生きる力にもつながる大事な拠点である。障がいのある若者やそれ以上の年齢の方たちの居場所、コミュニケーション、学び、体験の場等と生活支援を行っている「生活介護事業所」だが、支援学校卒業後の受け入れは簡単でないこともお話を伺うなかで知った。
「遠距離送迎ができない」「定員がいっぱい」など、医療的ケアの必要な18歳以上を対象とする居場所が不足していることが改めて明確となった。
立川市福祉施設交流連絡会 事業所ガイドブックによると、医療的ケアを受け入れできる生活介護事業所は、社協で実施している「マンボウ」「コスモス」の1か所。定員50名 現在最少年齢19歳、最高齢は65歳、平均年齢38歳となっている。ここでも受け入れ枠50人はいっぱいで、医療的ケアの必要な方の受け入れささらに限られ、通所の方は週2~3日とのこと。支援学校卒業後につながる居場所としては難しいと聞いており、立川市に新たな受け入れ場所設置を求める切なる声をお聞きした。
そこで、重症心身障がい児、医療的ケア児を地域で受け入れたいと事業所を立ち上げた事例を紹介する。お隣の昭島市で2017年にスタートした放課後デイサービス・キッズサポートてんとうむし。「重症の障がいを抱えた子どもたちとご家族が、安心して過ごせるように、子どもたちが地域の中で笑顔いっぱいに、穏やかな生活が続けられるように、そして、できる限り健康を維持していけるように、共に歩み、共に生きるまちづくりに尽力します」と理念を掲げ、0~18歳までの居場所をつくった。
代表を務める方は、理学療法士の経験を重ねる中、市内で障がい児を支援する事業所がなく、特に医療的ケアを必要とする重症心身障がい児については、近隣市町村にも支援事業所が少なく受け入れが難しいということ、重症の心身障がいのある子どもたちにとって、当たり前に地域でくらしていくということがどんなに大変な状況であるかということに心を寄せ、子どもたちの安定した生活の継続はもちろんのこと、日頃ケアにあたるご家族、特にお母さんの心身への負担軽減、レスパイト目的の支援も大変重要であるとし、2020年に新たな事業所「ロングサポート ラ・ナチュール」を放デイてんとうむしのお隣の場所に開所し、児童発達支援事業所が2階、生活介護事業所が1階という複合化で18歳以上の居場所を確保した。視察に伺わせていただいた日には、ちょうどてんとうむしを卒業した20歳前後の若者2名が生活介護事業所を利用しており、児童発達支援事業所を利用していた未就学児と一緒に「今日あったこと」「うれしかったこと」などを共有する帰りの会を合同で行っているように見えた。医ケアが必要であっても、重度の障がいがあっても、きちんと考え表現することが出来る子も多く、一般の方と同じようにはできないかもしれない、時間がかかるかもしれない、でも適切な支援があればコミュニケーションできるし、自分をありのまま受け入れてもらえる、こういった施設こそ、まさにいま必要だと改めて感じた。そして、学校卒業後は、成人として中高齢者受け入れの生活介護事業所ではなく、例えば放課後デイサービスから連続性のある生活介護事業所の開設により、その年齢に応じた発達応援、社会体験、地域交流等、必要とされる応援体制づくりに着手すべきではないか。仲間意識・連帯感も生まれ、自分の居場所として愛着がわき、また行きたい、次も楽しみといったような生活に潤いがでてくる居場所にしていくことが必要であると、当事業所の視察を通して実感した。
当時者への応援はもちろんのこと、ご家族へのサポートとしても立川市での設置が必要不可欠と強く感じ、若者が利用しやすい生活介護の居場所設置を求める。
A.本市としても、高校の卒業と同時に、いわゆる18歳の壁が存在することは認識している。重症心身障害者の方や医療的ケアを必要とする方を支援対象とする生活介護事業所については、事業所から開設の相談があったため、現在検討している状況。
災害時に備えて
ケアが必要な市民の災害時の対応について
Q.本年は、能登半島地震、継続する余震と、災害の重なる年であり、防災についてアンテナを高く活動を続けてきた。能登半島地震の頃はまだ私自身第2子の授乳中であり、妊産婦や乳幼児連れの場合の避難所生活における備え等について、前回質問させていただいた。今回は2つ目のテーマで取り上げた医療的ケアの必要な市民の生活を知っていくなかで、日頃ケアを必要とする皆さんがどんなに大変な生活をされているのか聞き、配慮の必要な方の防災について、より入念な計画が必要であると考えたことから質問させていただく。まず、総括的な質問として、配慮の必要な方の避難計画がどうなっているのか、現状等もあわせてお聞きする。
A.高齢者や障がい者など、避難行動要支援者名簿に掲載される方お一人お一人に災害時に迅速に避難できるよう、避難支援を行う人や避難先、避難方法等を事前に記載しておく個別避難計画を作成していくこととしている。現在、市では、個別避難計画を優先して作成する多摩川洪水浸水想定区域の対象者から順次個別避難計画の作成に取り組んでおり、昨年度は59名の計画を作成した。この区域には、本年8月1日現在244名の作成対象者が居住するところ、今年度はこのうち100名の計画を作成していくこととしており、引き続き避難支援の体制を整えてまいりたい。
Q.ケアが必要な市民の災害時の対応についてということで、要配慮者について聞く。妊産婦や乳幼児連れの家族が一次避難所に避難した場合、避難所運営で支援している内容は。
A.各一次避難所では、妊婦や乳幼児世帯などが安心して避難生活を送るため、食料や生活用品等の備蓄品による物資面の支援とともに、運営面では、体育館の中での間仕切りテントによるプライバシーの確保や教室等に乳幼児世帯優先居室や女性専用スペースを配置するなどの対応を行っていく。
Q.福祉避難所について聞く。立川市地域防災計画には、現在公立保育園6園と、民営化した保育園5園、ドリーム学園が乳幼児用、障害者用として3か所の福祉作業所が福祉避難所として指定されている。この計画ですと、市内の障がい者用区分が3か所合わせて最大受け入れ者数80人では、例えば身体障がい者だけでみても、市内全体の2%にも満たない状況で、とても少ないのではないかという印象なのだが、課題についてどのように捉えているか。
A.福祉避難所については、指定福祉避難所の指定を促進するとともに、事前に受け入れ対象となる要配慮者を調整して、人的、物的体制の整備を図ることで、災害時の直接の避難等を促進し、要配慮者の支援を強化することが課題であると考えている。
Q.それらの課題について、今後どのように取り組みを進めるべく協議など進めているか。
A.障がい者や要配慮者の福祉避難所については、必要となる設備や機能を考慮して、介護保険施設、有料老人ホーム、グループホーム、宿泊施設等との協定締結による福祉避難所の指定の拡大、また乳幼児用の福祉避難所については、平常時の利用状況を踏まえて、公立だけでなく私立保育園等との協定締結により、福祉避難所の指定の拡大を図ってまいりたい。このほか、ホテル、旅館など民間施設との協定を締結し、要配慮者の避難所ニーズに対応してまいりたい。
Q.医療的ケアが必要な、子どもを含む市民は、災害時の対応の計画はどのように進んでいるか。
A.医療的ケアを必要とする方など要配慮者への対応については、災害時には迅速な安全確保、安否確認、避難支援が必要となってくる。市では、災害発生後、生活支援班、子ども支援班を中心に安否確認と所在把握に努めるとともに、適切な援護を実施するため、避難所及び在宅の要配慮者の実態調査を行うこととしている。要配慮者の実態把握の結果に基づき、必要な場合は、緊急医療救護所や医療機関の医師等の意見を求めた上で、関係先との協議を行い、緊急入院、緊急一時入所や在宅援護などの緊急援護を実施する。
Q.個別避難計画について聞く。災害が起こらないことが一番良いのだが、計画を立てること自体は目的ではなく、いざという時にその計画がきちんと運用され、実際に使えるものにならないといけないと思っている。自治体によっては、ケアマネさんなどに協力していただいてその方の障がいを考慮し、個別避難計画に沿った避難訓練を行うところがあるようです。個別避難計画に合わせて訓練をする必要性についての見解は。
A.個別避難計画に沿った訓練は、必要と考えている。総合防災訓練においても、個別避難計画の避難支援を想定し、協定を締結している市内タクシー事業者と協力した要配慮者移送訓練を継続して実施している。今後も避難の実効性を高める訓練は重要と認識しているため、順次避難支援の体制を整えてまいりたい。
災害時のトイレ
Q.最後に災害時のトイレについて聞く。先日、立川四中で行われた立川市防災訓練に会派全員で参加した。そこで、マンホールトイレについて改めて確認させていただいたが、現在教育部が進めている計画では水泳指導の外部委託が進んでいる状況で、今後プールからの水源確保が難しくなった場合、マンホールトイレの水源はどのように確保する予定か。
A.災害時にマンホールトイレを使用していく際には、プールの水アを集水し、使用していくこととしている。このため、今後も平時からプールに水をため置き、災害時には生活用水としてマンホールトイレ等に使用していくほか、消防水利として活用していくこととしている。
Q.前回の私の一般質問において、みんなのトイレプロジェクトに参加してトイレトレーラー導入について求めたところ。調べを進めていくと、一口にトイレカー、トイレトレーラーといっても種類がいろいろあることが分かってきた。例えば普通車でけん引できるもの、車そのものにトイレ機能が搭載されているトイレトラックなどがある。品川区で導入したトイレカーは「トイレトラック」ということで、水洗トイレが4室あって、一番後方部の5室目は少し広くなっていて、水洗トイレだけでなく、車いすリフター、つまり車いすの方を持ち上げられて、オストメイトの方にも対応する多機能トイレ、おむつ交換台、ベビーキープなども備えられている。こういったトイレカーを導入する自治体が増えることで、災害時の相互支援時に、より多様な方が安心して安全に、清潔に、過ごせることにつながる。こちらは太陽光パネルも搭載され停電時にも活用できるという。また、トヨタとリクシルが共同開発されたモバイルトイレも注目されている。ご当地の豊田市が導入したトイレカーということだが、こちら普通車でけん引ができて、専用の工具を使えば大人二人でも移動することができる。設置すれば車いすユーザーの方はスロープから自分でトイレに行き、室内で方向転換することも可能なほどの広さがある。折り畳みのベッドも備え付けられており、介助が必要な方、姿勢を変えるためにベッドが必要な方も利用することができる。トイレカー・トイレトレーラー・トイレトラック、呼称はいろいろあるが、ユニバーサルデザインのものを導入する自治体も増えてきて、ケアが必要な方の災害時のトイレとしてもとても有効である。一時避難所ではトイレが課題となり、そのことで二次避難が必要な方などにとっては、こういった普及により福祉避難所の受け入れが足りていないという課題解消の一助にもなりえると考えた。前回の質問では、トイレトレーラーの導入に向け、積極的な情報収集を行うといったご答弁であったが、その後の状況は。
A.トイレカーについては、能登半島地震におけるトイレカー支援を行った自治体の好事例を踏まえ、都内においても導入を予定している自治体があることを承知している。この都内での導入予定の自治体に、調達スケジュールや平時の活用方法を確認するとともに、災害派遣トイレネットワーク団体へのヒアリング、費用面、運用面の課題等について情報収集を行ってきた。本市においてもトイレカー導入は被災者支援に大変有意義であると考えていることから、導入にむけ検討していく。
Q.導入された多くの自治体では、イベントなどに活用されていたり、実際に災害時の自治体間相互支援に役立てたりといった事例があるようだ。立川市においても、もし誰でもトイレが併設されるトイレトラックが導入されるようでしたら、トイレがないことでお出かけできないという多くの市民のお声を聞きますので、是非ニーズを調査していただきたい。車いす対応ができないところ、オストメイトの方向けのトイレがないところに出向くようにして、次はいつどこに行くか、市ホームページや公式ラインを活用いただけたら、普段トイレのことで外出を億劫に感じてしまっている方たちの、外出する契機になるなどプラスの効果を狙っていただきたいと考える。もちろん災害時の活用や相互支援が主眼であるかと思うが、より市民の利益につながり、市全体の活力につながっていくようなお取組みをお願いしたい。平時の活用についてはどのような協議が進んでいるか聞く。
A.トイレカーが導入された場合の平時の活用方法については、都内で導入予定の自治体に確認したところ、防災訓練やイベント等での周知に限った団体や、平時から屋外体育施設で活用する予定の団体など、各団体の考え方は様々である。仮に、本市がトイレカーを導入した場合には、平時における市民のニーズ等を踏まえるとともに、災害時には速やかに活用できる方策を検討していきたいと考えている。
本日は、ケアの必要な方やマイノリティーの方もありのまま自分のまま受け入れられて、大好きなまち・立川で自分らしく生きていけるため、その生活や人権が守られるために、立川市としてどんな応援をしていけるかという視点で質問を重ねさせていただいた。ぜひ、制度を使いたくても使えない、使いたい制度自体がない、そういった市民にも目を向けていただき、更なる行政サービスの向上にむけてのお取組みをお願いする。